離職率が高い業界ランキング|転職前に知るべき5つのポイントとは
企業名が入ります
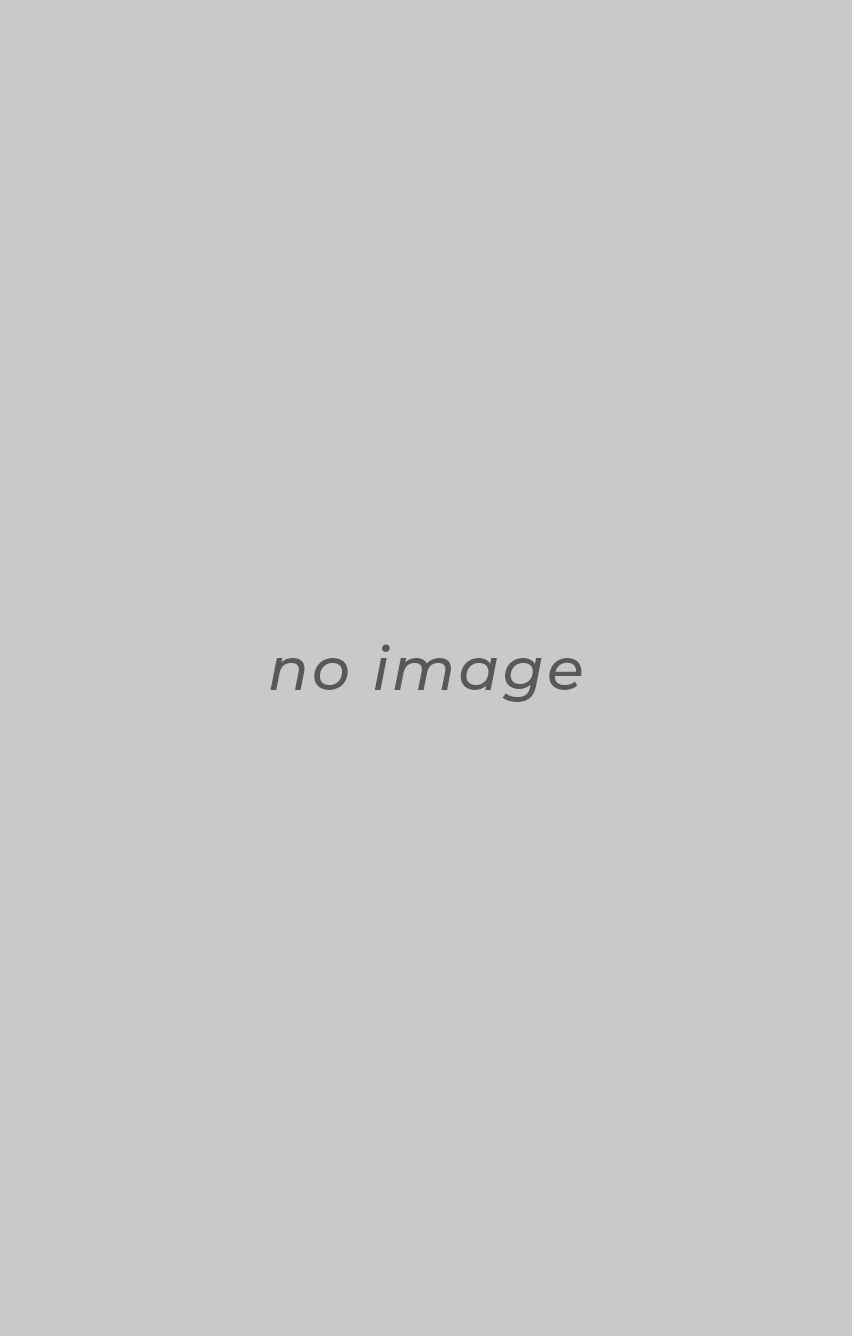
「転職するなら離職率が低い業界で働きたい」という方もいるでしょう。離職率が高い業界は、長時間労働や低賃金など、労働環境が過酷なケースも多いです。また、クレーム対応が多かったり、研修・育成制度が整っていないことも。
本記事では、離職率が高い業界をランキング形式でご紹介します。離職率の高さをチェックする方法や離職率の低い業界についても紹介するので、転職したい方はぜひ参考にしてください。
なぜ「離職率の高い業界」を知るべきなの?

転職活動で企業分析を行う際に、企業の離職率を気にする方も多いでしょう。転職や就職を考える際、「どんな業界か」だけでなく「どれくらい人が辞めているか」も重要な判断材料になります。
離職率が高い業界には、働き方や人間関係、待遇面に何らかの課題がある可能性があります。事前に離職率の高い業界を知っておくことで、自分に合わない職場を避け、長く働ける環境を選びやすくなります。ここでは、転職の際に離職率の高い業界を知っておくべき理由について紹介します。
離職率が高い=ブラックではないが注意は必要
離職率が高いからといって、すべての企業がブラック企業とは限りません。ただし、労働環境や人間関係に課題がある可能性もあります。
たとえば、介護・福祉業界では、体力的な負担が大きく、待遇面の不満が離職につながることがあります。また、飲食業界や小売・販売業界では、人と接する機会が多いため、人間関係で悩むケースも多いです。
転職後の後悔を防ぐためにも知ることは大切
転職後に「思っていた仕事と違った」と後悔しないためにも、あらかじめ離職率の高い業界を知っておくことが重要です。事前に業界の離職率を調べることで、ミスマッチを防ぎやすくなります。業務内容や労働条件だけでなく、企業の口コミや評判もあわせてチェックし、自分に合う環境かどうかを見極めましょう。
3年以内離職率と1年以内離職率の違い
3年以内離職率は、新卒社員が3年以内に退職する割合です。一方、1年以内離職率はより早期に辞めた人の割合を示します。厚生労働省の調査によれば、2024年の時点で、3年以内離職率は新規高卒就職者38.4%、新規大卒就職者34.9%となっています。また、1年以内離職率については、毎年1割近くの人が1年以内に離職しています。
出典:
厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」
厚生労働省プレスリリース「新規学卒就職者の離職状況を公表します」
離職率が高くても働くメリットとは?
一見ネガティブに思われがちな「離職率の高い職場」ですが、実はそこにも意外なメリットがあります。特にキャリアの初期段階や、自分を短期間で成長させたいと考える方にとっては、有益な選択肢となる場合もあります。
圧倒的な成長スピードを得られる
離職率が高い職場では、人手不足が常態化していることも多く、若手でもすぐに実践の場に立たされます。プレッシャーは大きいものの、その分早い段階で責任ある仕事を任されるため、短期間でビジネススキルが磨かれます。普通の企業で数年かかるような経験を、1年未満で得られることも珍しくありません。
キャリアの方向性を早く見極められる
離職率が高い職場では、仕事や人間関係における「向き・不向き」がすぐに明らかになります。早期に自分の適性を見極めることができるため、「とりあえず3年我慢」よりも、自分に合った環境を見つけやすいという利点があります。
競争環境の中でメンタルが鍛えられる
厳しい環境を乗り越えた経験は、のちのキャリアでも大きな財産になります。プレッシャーや多忙な日々に耐えた経験は、転職活動でも「タフさ」「柔軟性」「行動力」として高く評価されることがあります。
次の職場での評価が上がりやすい
離職率が高い職場で成果を出した人材は、他社から見ると「逆境でも成果を出せる人」として評価されやすくなります。特に営業職やスタートアップ業界では、このようなバックグラウンドが歓迎される傾向にあります。
離職率が高い業界5選

離職率が高い業界は、以下の5つです。
1.飲食業界
2.介護・福祉業界
3.小売・販売業界
4.教育業界(塾講師・保育士)
5.広告・出版業界
それぞれ解説します。
1. 飲食業界
飲食業界は、特に若年層の離職率が高い業界です。理由として、長時間労働や休憩の取りづらさ、休日の少なさが挙げられます。人手不足により一人あたりの業務負担が大きく、体力的・精神的にハードな現場が多いのが現状です。
さらに、アルバイトや非正規雇用の割合が高く、キャリア形成が難しい点も定着率を下げる要因となっています。
2. 介護・福祉業界
介護・福祉業界は、社会的な需要が高まる一方で、離職率の高さが課題です。介護職員処遇改善が進んでいるとはいえ、業務量に対して報酬が見合わないと感じる人が多くいます。
また、利用者や家族との関係構築に気を使う場面も多く、心身の負担が重なります。夜勤や不規則な勤務体制も、働き続ける難しさにつながっています。
3. 小売・販売業界
小売・販売業界は、接客業務や在庫管理、売上目標へのプレッシャーなど業務が多岐にわたります。シフト勤務が主で、土日祝日も働く必要があり、私生活とのバランスが取りづらい点が大きな離職理由です。
短期間で多くの人が入れ替わる傾向があり、職場の人間関係が安定しにくいのも特徴です。長期的なキャリア形成には工夫が必要な業界です。
4. 教育業界(塾講師・保育士)
教育業界の中でも塾講師や保育士は、子どもとの関わりにやりがいを感じる反面、離職率が高めです。塾講師は夜間勤務が多く、保護者対応も精神的な負担になります。保育士は人手不足が常態化しており、業務の多さと給与水準の低さが不満となりやすいです。職場のサポート体制や働き方改革が進んでいないと、長く続けるのが難しい職種です。
5. 広告・出版業界
広告・出版業界は、華やかなイメージがある一方で、締切に追われる日々や激しい競争にさらされやすい環境です。長時間労働や突発的な対応も多く、ワークライフバランスを保ちにくい点が離職の主な理由です。創造性を求められる仕事ですが、評価が不透明なこともあり、心身ともに消耗しやすい傾向があります。継続するには適性と覚悟が求められます。
離職率が高い業界の3つの共通点
転職先を選ぶ際に気をつけたいのが、離職率の高い業界です。人の出入りが多い職場には、働き方や人間関係、待遇などに何らかの課題が潜んでいることもあります。後悔しない転職をするためには、その業界に共通する特徴を知っておくことが大切です。
ここでは、離職率が高くなりやすい業界に見られる3つの共通点を紹介します。
1. 労働環境が過酷(長時間・低賃金)
離職率が高い業界では、長時間労働や休みの少なさが日常的です。飲食業や介護業では、慢性的な人手不足により一人あたりの業務負担が重くなっています。
また、給与水準が低めで、働きに見合った報酬が得られないと感じる人も多いです。このような状況が、心身の疲労や不満を招き、退職の大きな要因になります。
2. 感情労働・クレーム対応が多い
顧客対応が中心となる職種では、感情をコントロールしながら働く場面が多くなります。保育士や小売業の販売員、コールセンターのオペレーターなどはその代表例です。
特にクレーム対応は精神的なストレスが大きく、長く働き続けるには高い忍耐力が必要です。このような感情労働の蓄積が、離職の一因となっています。
3. 研修・育成制度が整っていない
教育体制が不十分な職場では、入社後に何をすれば良いか分からず、不安を感じやすくなります。十分な研修がないと、業務をこなす自信を持てず、早期離職につながることがあります。特に新卒や未経験者にとって、サポートの有無は職場への定着に大きく影響します。人を育てる文化がない職場は、結果的に人が定着しにくい傾向にあります。
離職率の高さをチェックする方法
ここまで離職率が高い業界や共通点について解説してきましたが、転職先や就職先を選ぶうえで、離職率の高さを事前に知っておくことはとても重要です。
職場の定着率を確認することで、働きやすさや人間関係の良し悪しを判断する手がかりになります。ここでは、離職率の高さを見極める具体的なチェック方法を解説します。
求人票から読み取る3つのサイン
求人票には、離職率のヒントが隠れています。「未経験歓迎」「大量採用」「研修充実」などの文言がある場合、離職者が多く常に人手不足の可能性があります。
また、「残業あり」「シフト制」などの勤務条件もチェックポイントです。同じ求人を長期間掲載している企業にも注意が必要です。表現の裏にある意図を読み取ることが大切です。
転職サイトの口コミ・評判の活用方法
転職サイトの口コミや評判は、実際に働いた人の声が集まる貴重な情報源です。特に「上司・同僚との関係」「退職理由」「残業時間」などの項目は離職率の高さを推測する材料になります。
ただし、投稿者の主観が強く反映されているため、複数の意見を比較しながら判断することが重要です。信頼できるサイトを活用し、情報の偏りに注意しましょう。
面接での質問例:職場のリアルを引き出すコツ
面接では、質問の仕方によって職場の実情を引き出すことができます。「前任者はなぜ退職されたのですか?」「残業は月に何時間ほどありますか?」など、具体的な質問をしてみましょう。
「チームの平均勤続年数」も離職率の目安になります。曖昧な回答や話を逸らされる場合は、職場に何らかの問題がある可能性もあるため注意が必要です。
離職率の低い業界はどこ?定着して働ける業種を紹介

働きやすい職場を選ぶうえで、離職率の低さは重要なポイントです。離職率が低い業界は、職場環境や労働条件が整っているケースが多く、長く安心して働ける傾向があります。
転職や就職で「次こそは長く続けたい」と考えている方に向けて、定着率の高い業界やその特徴について紹介します。
定着して働ける業種を紹介するので、転職活動中の方はぜひ参考にしてください。
インフラ系(電気・ガス・水道)
電気・ガス・水道などのインフラ業界は、生活に不可欠なサービスを提供するため、景気に左右されにくく、雇用が安定しています。労働時間も比較的整備されており、福利厚生が手厚い企業が多いのも特徴です。業務内容は専門性が高いですが、その分スキルを磨けば長期的に働きやすい環境が整っています。離職率の低さは業界全体の特徴と言えます。
医療機器・製薬業界
医療機器や製薬業界は、少子高齢化の進行により今後も成長が見込まれる分野です。安定した業績や充実した教育制度により、働く人の満足度が高く、離職率も比較的低めです。専門知識を活かしながら社会貢献ができることも魅力のひとつです。大手企業が多く、福利厚生やキャリア支援も整っているため、長く働ける環境を求める方に適しています。
公務員・学校法人などの教育業界
公務員や学校法人は、安定した雇用と明確な給与制度が整っており、定着率の高い業界です。特に正規雇用で働く場合、長期的なキャリア形成がしやすく、福利厚生も充実しています。
また、業務の内容やスケジュールが比較的安定しているため、プライベートとの両立もしやすい点もメリットです。安定志向の転職者にとって、有力な選択肢となります。
まとめ
転職を成功させるには、離職率が高い業界の特徴を理解し、自分に合った職場を選ぶことが重要です。飲食・介護・小売などは、長時間労働や感情労働、研修不足などが原因で離職率が高めです。一方、インフラや医療機器、公務員などは安定した環境が整い、定着率が高い傾向があります。求人票や口コミ、面接で情報を集め、後悔のない転職を目指しましょう。
share on



 転職相談はこちら
転職相談はこちら お問い合わせ
お問い合わせ
