20代に「静かな退職」が増加中?|理由・背景・キャリアの選択肢を徹底解説
企業名が入ります

「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉を耳にする機会が増えてきました。これは会社を辞めるのではなく、業務を必要最低限にとどめ、仕事以上にプライベートや心身の健康を優先する姿勢を指します。近年、特に20代の若手を中心に静かな退職が広がっており、その背景には働き方や価値観の多様化があります。本記事では、静かな退職が増加する理由や職場への影響、そしてキャリアを前向きに築くための選択肢について解説していきます。
静かな退職とは?注目される背景と20代に広がる傾向
「静かな退職」は、会社を辞めずに仕事への関わり方をセーブする新しい働き方のスタイルとして注目を集めています。特に20代の若手世代に広がっているのは、働き方に対する価値観の変化が背景にあるためです。キャリアアップよりも心身の健康やワークライフバランスを重視する傾向が強まり、プライベートを犠牲にしない選択肢として選ばれやすくなっています。今や一時的な流行ではなく、若手社員に根付く新しいキャリア観といえるでしょう。
「静かな退職」とは何か?従来の退職との違い
「静かな退職」は、物理的に退職届を出して職場を離れることを意味しません。従来の退職が「会社を辞める行動」であるのに対し、静かな退職は「与えられた業務を最低限こなす」という働き方を選ぶ姿勢です。長時間労働や過度な責任を避ける一方、給与や地位の安定は確保したまま、エネルギーを自分の人生やプライベートに振り分けます。このスタイルは消極的に見える一方で、心身を守る合理的な選択とも捉えられ、20代を中心に急速に浸透しています。
20代の若手社員を中心に増加する理由
20代で静かな退職が増えている大きな理由は、価値観と働き方の変化です。過去の世代は「会社に尽くすこと」が美徳とされましたが、現代の若手社員は「自分の人生を大切にすること」に重きを置きます。成果が正当に評価されない、昇給が見込めない、長時間労働が常態化しているといった職場環境では、積極的に働く意欲を失い、静かな退職という形を選びやすくなります。また、SNSや調査データを通じて同世代の価値観に触れやすいことも、この動きが広がる一因となっています。
働き方・価値観の変化と職場の影響
静かな退職の広がりは、20代の「仕事とプライベートの境界を大切にしたい」という価値観の変化に直結しています。かつては「多少の我慢がキャリアにつながる」とされてきましたが、今は心身を削る働き方を選ばず、自分のペースで成果を出すことを望む人が増えています。その結果、企業にとってはエンゲージメントの低下や離職リスクの増大といった影響も無視できません。職場は単なる「労働の場」ではなく、個人の成長や幸福度に直結する場所として再定義されつつあります。
海外と日本での比較から見る静かな退職の位置づけ
静かな退職はアメリカで注目され、その後日本でも広がりを見せています。海外ではリモートワークやジョブ型雇用の普及が背景にあり、仕事と私生活を明確に分ける文化が根付いています。一方、日本は「組織への忠誠心」や「長時間労働」が根強く残るため、静かな退職はまだ新しい概念として受け止められています。しかし、20代を中心に働き方の意識が変化しており、近い将来、日本でも静かな退職がスタンダードな選択肢として浸透していく可能性が高いでしょう。
20代が静かな退職を選ぶ理由とその原因

静かな退職は一見「やる気がない」ように見えますが、その背景には若手社員が直面するリアルな課題があります。やりがいや成長の欠如、職場の人間関係、長時間労働や給与への不満など、20代が働く中で抱える問題は多岐にわたります。さらにコロナ禍を経て働き方が大きく変化したことも、この動きを加速させています。静かな退職は単なる「甘え」ではなく、時代の流れと職場環境が生んだ必然的な選択肢ともいえるでしょう。
やりがいや成長機会を感じられない職場環境
20代はキャリア形成の初期段階にあり、挑戦や成長を求める意欲が高い世代です。しかし、単純作業ばかりでスキルアップの機会が少なかったり、努力が正当に評価されない職場では、やりがいを見出すのが難しくなります。その結果「この職場にいても成長できない」と感じ、仕事に積極的に取り組むモチベーションが下がり、静かな退職という選択につながるケースが増えています。キャリア初期の停滞感は、特に若手世代にとって深刻な要因となっています。
人間関係や上司との関係によるストレス
職場での人間関係は、静かな退職を選ぶ大きな引き金となります。特に20代の若手社員は、上司や先輩からの過度な指示やコミュニケーションの断絶にストレスを感じやすい傾向があります。自分の意見が尊重されない、風通しの悪い環境に置かれると、前向きに働く姿勢を保つのが難しくなります。こうした状況では「辞める」よりも「力を抜いて関わる」方が現実的で安全な選択となり、静かな退職が心の防衛策として機能しているのです。
長時間労働や給料・評価に対する不満
長時間労働が常態化しているのに、給料が見合わない、努力しても評価が不透明―。こうした不満は20代の若手社員にとって深刻なストレスになります。働いた分が正しく報われないと「頑張る意味がない」と考えるのは自然な流れです。特に、経済状況が不安定な中で昇給やキャリアパスが不明確な場合、無理に成果を追うよりも「最低限の仕事で給与を確保する」という選択に傾きやすくなります。これも静かな退職が広がる大きな原因のひとつです。
コロナ禍以降の働き方の変化が与える影響
コロナ禍を経てリモートワークや柔軟な働き方が普及し、「仕事と生活のバランス」を重視する意識が一気に高まりました。それまで「会社中心」で働いていた人も、在宅勤務を経験することで「自分の時間の大切さ」に気づくようになったのです。その結果、過度な働き方に疑問を持ち、必要最低限の関わりにシフトする静かな退職の選択肢が広がりました。特に20代の世代は、この変化を柔軟に受け入れ、実践に移しやすい層といえるでしょう。
「甘え」ではなく背景から生まれる必然的な選択肢
静かな退職は「若者の甘え」と批判されることもありますが、実際には社会や職場環境がもたらした必然的な流れです。過度な負担に対し報酬や成長の機会が見合わない現状で、無理を続ければ心身の不調や離職に直結しかねません。そのため「静かに仕事をセーブする」という行動は、自分を守る合理的な手段といえます。20代がこの選択をするのは、未来のキャリアを守るための一歩であり、個人の価値観を反映した自然な判断と考えられるのです。
静かな退職が増加することで起こる影響
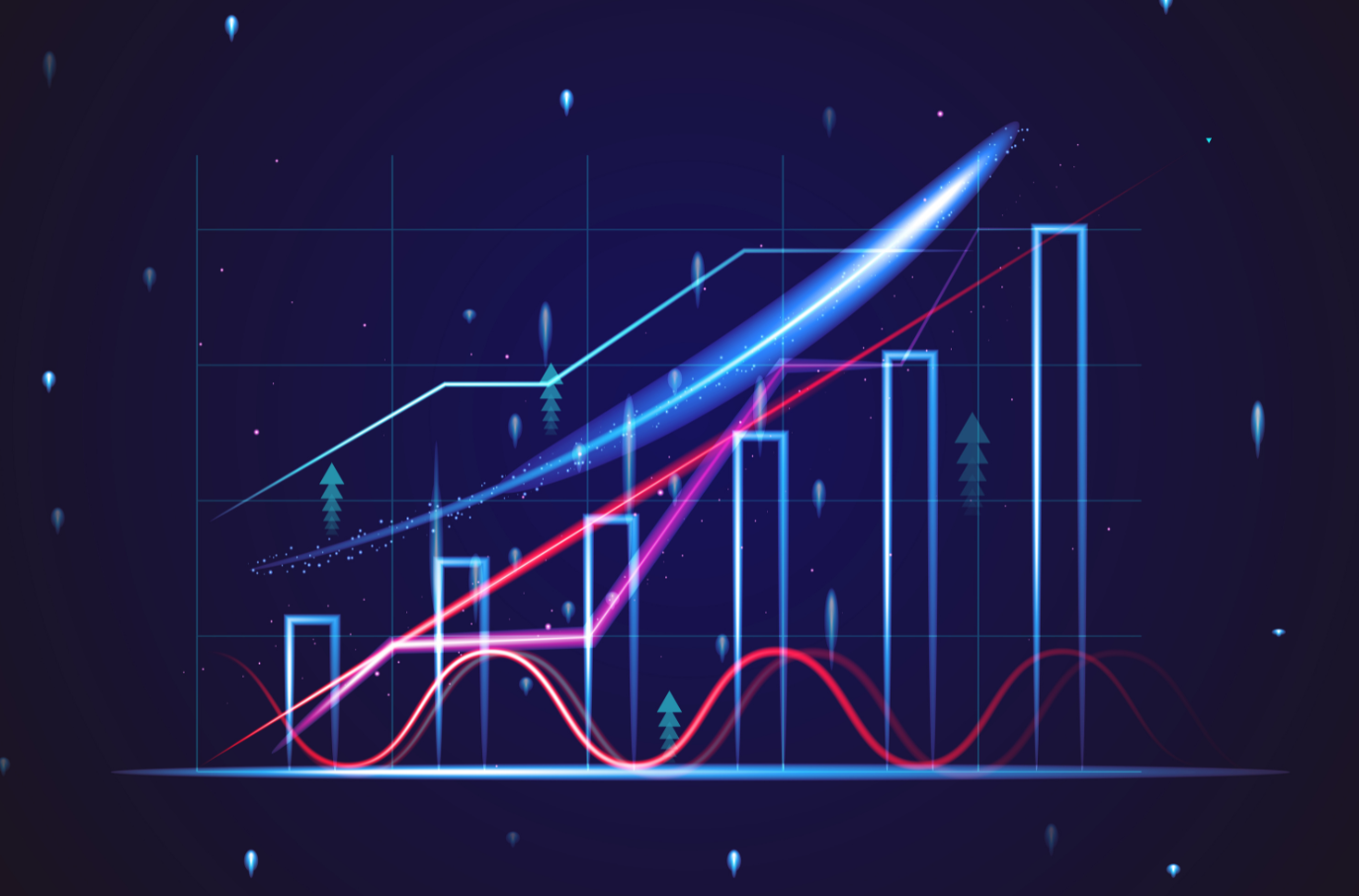
静かな退職は個人の働き方の選択肢として広がる一方で、企業や社会全体に少なくない影響を与えています。20代の若手世代が静かな退職を選ぶことは、組織の生産性や人材戦略に直結する課題です。本章では、経営への影響や社員本人のメリット・デメリット、世代別の傾向などを整理しながら、今後の働き方のあり方を考えていきます。
企業や経営への影響と今後の働き方の課題
社員が静かな退職を選ぶと、一見「離職」には至らないため表面化しにくいですが、生産性やエンゲージメントの低下を引き起こします。企業にとっては、プロジェクトの停滞や人材の流動化リスクにつながり、長期的には競争力の低下を招く可能性があります。さらに、経営層や人事部門が「社員がなぜ静かな退職に至るのか」を把握できないと、施策の改善も進みません。今後は働き方改革をより実効性のある形で推進し、個々人のキャリア観に寄り添った仕組みを整えることが課題といえます。
社員本人にとってのメリット・デメリット
静かな退職は、社員本人にとって「過剰な負担を回避できる」というメリットがあります。無理に頑張り続けて心身を壊すよりも、一定の距離感を保ちながら働くことで、自分の生活や健康を守れるのは大きな利点です。しかし一方で、キャリア形成の停滞や評価・昇給のチャンスを逃すというデメリットも存在します。20代にとっては「守り」と「成長」のバランスが難しく、長期的なキャリアをどう描くかを意識する必要があります。
20代退職者の割合や傾向データから見る現状
各種調査では、20代の若手世代で静かな退職を選ぶ傾向が強いことが示されています。特に20代後半から30代前半は、キャリアの方向性を模索する時期であり「無理して会社に尽くすよりも、自分の価値観を優先したい」と考える割合が高いのが特徴です。退職者全体の中でも、この世代の「静かな退職者層」の比率は年々増加しており、企業にとっても無視できない人事課題となっています。今後はデータを基にした対策が不可欠でしょう。
世代別に比較する「静かな退職」の特徴
世代別に見ると、20代の静かな退職は「将来への不安と挑戦欲求」が背景にあります。一方で40代以降では「家庭との両立」や「体力の低下」による働き方の見直しが多く、動機に違いが見られます。若手世代の場合、まだキャリアの可能性が広く転職市場でも選択肢が多いため「静かに働き方を変える」ことが次の行動につながりやすいのです。つまり、静かな退職は単なる消極的行動ではなく、世代ごとの価値観やキャリア状況を反映した選択肢といえます。
静かな退職を選ぶ前に知っておきたい対策と選択肢

静かな退職を選ぶ前に、まずは自分自身の働き方やキャリアを見つめ直すことが重要です。心身の健康を維持しながら、今の職場で改善できる点や、自分にとって最適なキャリアパスを整理することで、無理に仕事をセーブする前に前向きな選択肢が見えてきます。本章では、心身ケアや相談、転職・副業などの具体的な方法を紹介し、静かな退職を回避するための考え方を整理します。
心身のケアとキャリアの自己分析を実践する
長時間労働や過剰なストレスにより、心身の健康が損なわれると静かな退職を選ぶ可能性が高まります。まずは休息や趣味の時間を確保し、精神的な負担を軽減することが重要です。また自己分析を行い、自分の価値観・スキル・キャリア目標を明確にすることで、今の職場でやるべきことや改善点が見えてきます。健康と自己理解の両方を意識することが、建設的な行動につながります。
信頼できる人への相談や質問で視野を広げる
悩みや不満を一人で抱え込むと、静かな退職を選びやすくなります。信頼できる同僚や先輩、友人に相談することで、自分では気づかなかった解決策や視点を得られます。また、上司への質問やフィードバックを積極的に行うことも効果的です。これにより、仕事のやり方や評価の透明性が向上し、必要以上に力を抜く行動を避けることができます。
転職・副業など新しい働き方を検討する方法
現職での改善が難しい場合は、転職や副業など柔軟な働き方を検討するのも一つの手です。転職市場では、20代・30代の若手を対象に週休制度や裁量労働制を導入する企業も増えており、自分の価値観に合った環境を選ぶことで、静かな退職を避けながら成長できます。副業を通じてスキルや収入を補完する方法も、キャリア形成の選択肢を広げる重要な手段です。
静かな退職から「転職」へ行動する若手が増える理由
静かな退職を経験する若手の中には、自分のキャリアや価値観を見直した結果、転職に踏み切る人も増えています。無理に現職に縛られるのではなく、自分に合った職場で能力を発揮したいという意識が高まっているためです。また、20代・30代は市場価値が高く、転職によるキャリアアップや給与改善の可能性も大きく、静かな退職を契機に行動を起こすケースが目立ちます。
まとめ:静かな退職はゴールではなくキャリアを見直すサイン

20代で「静かな退職」を選ぶことは、決して消極的な行動ではなく、自分の働き方やキャリアを見直すサインです。現状に不満や不安を抱えたまま過ごすよりも、今の状況を整理し、自分に合った選択肢を考えることが重要です。本章では、次の一歩として取るべき行動やプロのサポートの活用方法について解説します。
働き方に悩む20代に必要なのは「次の一歩」
静かな退職を経験している若手に必要なのは、現状を受け入れつつも積極的に次の行動を検討することです。自己分析や相談を通じて、自分の価値観やスキルに合った働き方を見つけることが、将来的なキャリア形成につながります。行動を起こすことで、漠然とした不安を具体的な選択肢に変えられるのです。
転職で失敗しないためにはプロのサポートが不可欠
転職を検討する際、情報の偏りや判断ミスにより失敗するリスクがあります。特に20代は市場価値が高い反面、経験や知識が不足していることも。プロの転職エージェントを活用することで、自分に合った企業の提案や面接対策、年収交渉など、失敗を避けるためのサポートを受けられます。
Cocottoの転職エージェントがあなたのキャリア形成を支援します
Cocottoの転職エージェントでは、20代の求職者のキャリア状況や希望に応じて、最適な求人提案や面接サポートを行っています。静かな退職をきっかけにキャリアを見直す方にも、生活や働き方、給与面まで幅広く考慮したアドバイスを提供。まずは無料相談から、一緒に理想の働き方・キャリアを見つける一歩を踏み出しましょう。
\ あなたの魅力を最大限引き出す転職を、Cocottoが全力サポート! /
◆完全無料で利用できるCocottoの転職支援サービスはこちら
◆面接対策・求人紹介・キャリア相談までお気軽にどうぞ!
share on



 転職相談はこちら
転職相談はこちら お問い合わせ
お問い合わせ

