新卒で転職してもいい?タイミングと注意点を徹底解説
企業名が入ります
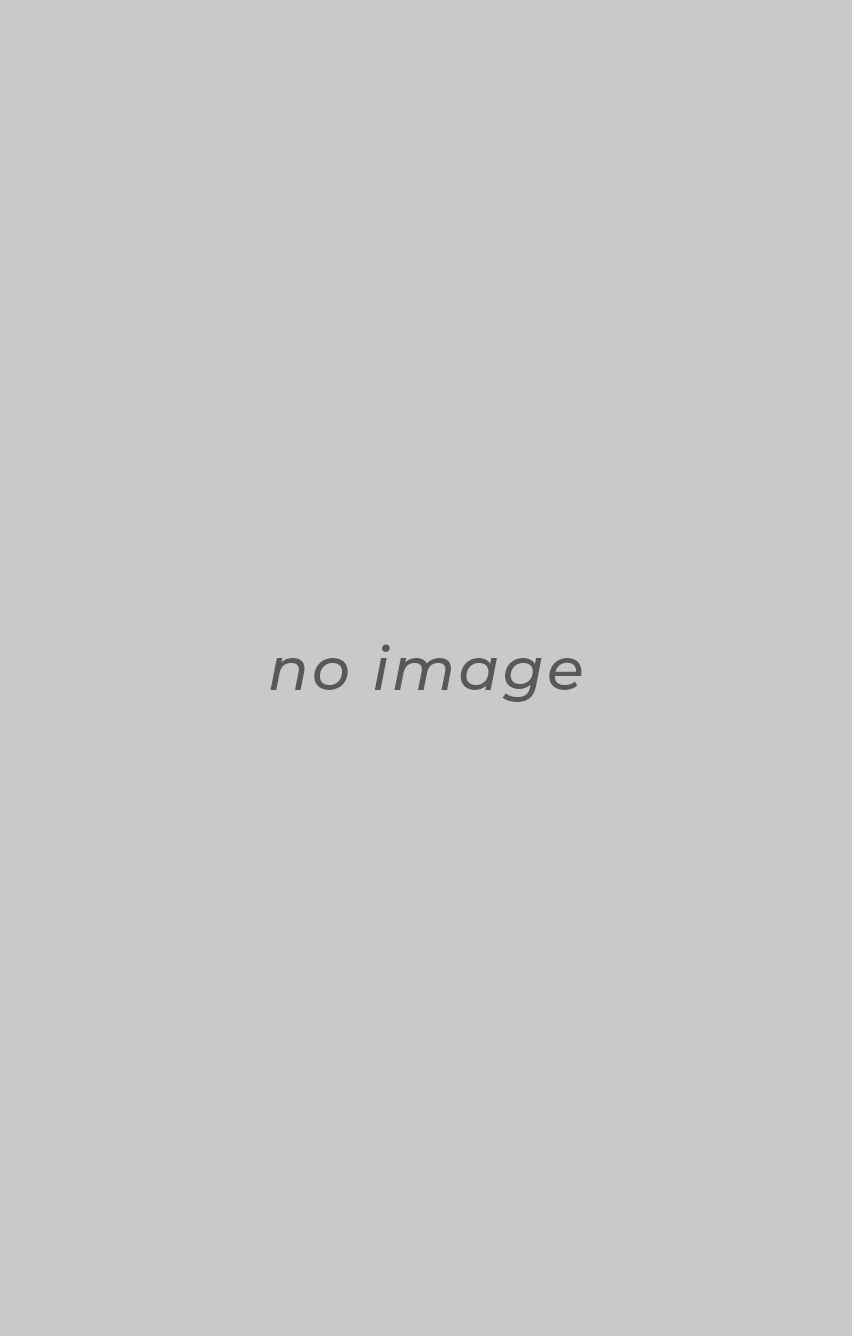
新卒で転職する人はどれくらいいる?まずは現状をチェック
新卒の早期離職率と「転職=失敗」ではない理由
厚生労働省のデータによると、新卒入社から3年以内に退職する人は約3人に1人。つまり「新卒で転職するのは珍しくない」というのが現実です。かつては「早期退職=根性がない」と見られがちでしたが、現在ではミスマッチの修正やキャリアの見直しと捉える企業も増えてきました。大切なのは「なぜ辞めたか」よりも「その経験から何を学び、次にどう活かすか」です。早期転職は失敗ではなく、前向きな再スタートにも十分なり得ます。
転職理由に多いものとは?人間関係・業務内容・社風のミスマッチ
新卒の転職理由として多く挙げられるのが、人間関係のストレス、思っていた仕事内容とのギャップ、社風が合わないといった“ミスマッチ”です。入社前に十分な情報が得られなかったり、配属先の運やタイミングに左右された結果、自分に合わない環境でモチベーションを失うケースも少なくありません。ただし、こうした理由はよくあるものなので、必要以上に自分を責める必要はありません。大事なのは、その違和感を放置せず冷静にキャリアを見直すことです。
転職に適したタイミングは?「いつから」がベストかを解説
社会人1年目・2年目・3年目、それぞれの転職メリットとリスク
社会人1〜3年目は、転職のタイミングとしてよく検討される時期です。1年目での転職は「早すぎるのでは?」と不安に思いがちですが、自分に合わない職場で無理を続けるより、早めに方向転換する方がプラスになるケースもあります。2年目以降になると実務経験や社会人スキルも身につき始め、転職市場での評価も高まりやすくなります。3年目は「ある程度仕事をやりきった」と自信を持って転職できる反面、責任あるポジションが増えて動きづらくなることも。それぞれのメリット・リスクを冷静に見極めましょう。
転職活動に向いている時期(春・夏・秋・冬)と企業の動き
転職において“季節”も重要な要素です。春(3〜4月)は新年度に向けた人材補充が多く、未経験者や第二新卒の採用が活発になります。夏(6〜8月)はやや求人が減る時期ですが、じっくり自己分析や準備を進めるには最適です。秋(9〜10月)は年度の中間で求人が再び増え、企業の動きも活発になります。冬(12〜1月)は採用活動が一時的に落ち着く傾向がありますが、1月以降は新卒採用と並行して中途採用も増加します。どの時期にもメリット・デメリットがあるので、焦らず自分に合ったタイミングを見て動くことが大切です。
「早すぎる転職」はアリ?1年未満の転職成功事例と注意点
「入社して1年も経たないうちに転職するのは印象が悪いのでは…」と不安になる方も多いですが、必ずしもマイナス評価にはなりません。特に明確な理由や前向きな転職目的がある場合、ポテンシャル採用としてチャンスを得ることも可能です。ただ注意したいのは、転職理由の伝え方。ネガティブな印象を与えず、学んだことや次の職場で実現したいことを軸に語れるように準備しましょう。また短期離職が続かないよう、自分に合った職場選びが何より大切です。
同職種へ転職する場合の注意点
今の職種が自分に合っていると感じつつも、職場環境や働き方に不満を抱えている場合は、同職種での転職を考える方も多いでしょう。その場合、注意すべきは「転職理由」と「キャリアの一貫性」です。同じ職種でも仕事内容や文化は企業によって異なるため、業務内容や評価制度をしっかり確認することが重要です。また、採用担当者から「なぜ今の会社ではダメだったのか?」と問われることが多いため、前向きな理由を明確に伝えられるようにしておきましょう。
未経験職種へ転職する場合の注意点
未経験の職種にチャレンジする場合、熱意と将来性をどう伝えるかが鍵となります。即戦力としてのスキルはなくても、ポテンシャルや成長意欲を感じてもらえればチャンスは広がります。ただし、理想だけで転職を決めるのは危険です。仕事内容や必要なスキルについて事前にリサーチし、自分の経験がどう活かせるかを言語化しましょう。また、転職後のギャップを防ぐためにも、職種理解を深めた上で意思決定することが大切です。短期離職を繰り返さないためにも慎重に準備をしましょう。
新卒が転職で失敗しないために押さえるべきポイント
自己分析・スキルの棚卸しを怠らない
転職を成功させるためには、まず「自分を知ること」が欠かせません。自己分析では、自分がどんなことを得意・不得意としているのか、どんな価値観や働き方を大切にしているのか、どんな職場環境が合うのかを明確にしましょう。また、これまでの経験から得たスキルや強みも整理しておくことが大切です。社会人としての経験が浅くても、学生時代の活動や現職での実績からアピールできることは必ずあります。棚卸しをすることで、志望動機や自己PRに説得力が増しミスマッチを防げます。
求人選びで見るべきポイント:職種・企業・将来性
求人選びでは、「職種」「企業のカルチャー」「将来性」の3つに注目しましょう。自分のやりたい仕事かどうかの気持ちの面での判断ではなく、その職種でどのようなキャリアが描けるか、努力すれば実現可能なのかどうかのチェックが必要です。また企業の理念や働き方、評価制度が自分に合っているかも重要な判断基準です。加えて、安定性や成長性といった将来性にも目を向けておくことで、入社後のギャップや早期離職のリスクを減らせます。見た目の条件だけでなく、中身をしっかり比較することが大切です。
転職理由の伝え方で印象は大きく変わる
面接で必ず聞かれる「転職理由」は、伝え方ひとつで印象が大きく変わります。「人間関係が悪かった」「思っていた仕事と違った」といったネガティブな内容も、単に不満を述べるのではなく「自分がどう感じ、どんな環境で力を発揮できるか」といったポジティブに変換して伝えるのがコツです。採用担当者は、あなたが転職を通じて何を実現したいのかを知りたがっています。前向きな目的意識をもとに、自分の言葉で誠実に説明することで、好印象につながります。
第二新卒との違いとは?採用側が見ているポイント
「新卒」と「第二新卒」の定義と違い
「新卒」とは、学校を卒業してから初めて正社員として就職する人のことを指します。一方で「第二新卒」は、新卒で一度就職した後、比較的短期間(一般的には入社後3年以内)で転職を考える若手層を意味します。どちらも社会人経験が浅い点では共通していますが、第二新卒は就業経験がある分、企業でのマナーや基本的なビジネススキルがあると評価されやすい傾向にあります。この違いを理解した上で、自分の立場にあった転職活動を行うことが大切です。
企業が第二新卒を歓迎する理由と求めるスキル
多くの企業が第二新卒を積極的に採用する理由は、成長ポテンシャルと柔軟性にあります。新卒と違って、社会人としての基礎があるため即戦力に近く、かつ前職での癖が定着していないため、自社のカラーに染めやすいという利点があります。企業は、ビジネスマナーや基本的なコミュニケーション能力、協調性といったスキルを重視する一方で、「なぜ転職したいのか」「今回どう活躍したいのか」といった目的意識や熱意もチェックしています。自分なりの転職理由と将来のビジョンをしっかり持ちましょう。
第二新卒としての採用で注意すべきこと
第二新卒として転職を目指す際に注意したいのは、「短期離職=我慢できない人」と見られないようにすることです。面接では、退職理由や転職の動機が必ず問われます。ここでネガティブな印象を与えてしまうと、どんなスキルがあっても採用に至らない可能性があります。大切なのは、前職から学んだことや転職によって実現したいビジョンをポジティブに語る姿勢です。また応募先の企業文化や職種との相性をしっかり見極め、同じミスマッチを繰り返さないよう慎重に進めましょう。
転職前に現職でやっておくべき準備とは
スキルアップ・業務経験の積み方
転職を考え始めたからといって、現職での仕事をおろそかにしてはいけません。むしろ、転職までの期間を使って、できる限りスキルや経験を積み上げておくことが重要です。たとえば、プロジェクトのリーダーを任されたり、後輩の指導を経験したりと、少しでも自分の職務の幅を広げられるように意識しましょう。こうした実績は、転職活動時のアピール材料になりますし、次の職場でも活かせる強みとなります。「辞めるから」ではなく「次につなげるために働く」という意識が、結果的に自分を必ず助けます。
社内の人間関係や評価を円満に保つコツ
転職を意識していても、現職での人間関係や評価を崩さないことはとても大切です。退職の意思を伝えるまでの間も、誠実な態度と丁寧な仕事を心がけることで、周囲からの印象が大きく変わります。また、いざ退職となったときに円満に送り出してもらえるかどうかは、その人の日頃の姿勢に左右されます。業務の引き継ぎや最後まで責任を持った対応ができれば、「どこに行っても活躍できる人」という評価にもつながります。将来的に再びつながる可能性もあるため、「どうせ辞めるから…」ではなく今ある関係性は大事にしておきましょう。
転職活動と並行して準備したいこと(応募書類・面接対策など)
現職を続けながら転職活動をする場合は忙しさとの戦いとなるため、事前の準備がカギとなります。まずは履歴書や職務経歴書を早めに整え、自分の強みや経験を整理しておきましょう。あわせて、よく聞かれる質問への回答を用意するなど、面接対策も進めておくと安心です。休日や業務後の時間をうまく使い、無理のないスケジュールを組むのがポイントです。忙しい中での転職活動は大変ですが、現職を続けながら転職活動を行うことはスムーズに次のステップへ進むことができるので、とても賢いやり方です。忙しい中でも一歩ずつ着実に進めましょう。
退職を決めたら…伝えるタイミングと伝え方のマナー
退職の意思を伝えるベストなタイミングはいつ?
退職の意思を伝えるタイミングは「遅すぎず、早すぎず」が理想です。一般的には退職希望日の1〜2ヶ月前が目安とされ、引き継ぎや業務調整に十分な期間を確保することがマナーです。特に繁忙期を避ける配慮も大切。直属の上司に相談する前に同僚へ話すのはNGなので、順序を守ることもポイントです。初めての退職は不安も大きいですが、冷静にスケジュールを組み立てることで、周囲との信頼関係を保ちながら円満に退職することができます。
誰に、どう伝える?円満退職に必要なコミュニケーション
退職の意思は、まず直属の上司に口頭で伝えるのが基本です。「お時間よろしいでしょうか」と丁寧に切り出し、退職の理由と希望時期を明確に伝えましょう。この際、感情的にならず前向きな姿勢で話すことが大切です。また退職理由を聞かれたときは、「キャリアの方向性」や「新しい挑戦」など、ポジティブな表現を心がけると印象が良くなります。メールやチャットで先に伝えるのは避け、しっかりと対面またはオンラインで話すことが円満退職への第一歩です。言いにくいとは思いますが、社会人として果たすべき責任です。勇気を出して伝えましょう!
引き継ぎ・最終出社・内定後スケジュールの立て方
退職が決まったら、内定先への入社日と現職の最終出社日から逆算してスケジュールを組みましょう。まずは業務の引き継ぎリストを作成し、後任やチームが困らないよう丁寧に準備を進めることが重要です。また、最終出社日には備品返却や社内挨拶などやるべきことが多いため、余裕を持った計画が不可欠です。引き継ぎや退職手続きをスムーズに終えることで、前職への感謝の気持ちを示すことにもなり、次の職場でも気持ちよくスタートを切ることができます。
ひとりで悩まず、転職のプロに相談しよう
Cocottoの転職エージェントが新卒・第二新卒に強い理由
Cocottoは新卒・第二新卒のサポートに特化した転職エージェントです。20代の転職市場に精通したキャリアアドバイザーが、社会人経験の浅い方でも安心して転職活動を進められるよう丁寧に伴走します。転職理由の整理から自己PRのアドバイス、求人紹介、面接対策(模擬面接)まで一貫して対応します。業界の動向や企業の“リアルな内情”にも詳しく、ミスマッチを防いだ提案が可能です。「こんな理由で転職してもいいのかな…」という悩みも、遠慮なく相談してください。
あなたに合った仕事・職種をプロの視点で見つけます
やみくもに求人へ応募しても、自分に本当に合った仕事にはなかなか出会えません。Cocottoでは、あなたの価値観・適性・将来像を丁寧にヒアリングし、プロの視点で最適な職種や働き方をご提案します。「なんとなく今の仕事が合わない」「自分に合った仕事が分からない」という声にも多く向き合ってきたからこそ、キャリアの軸を一緒に見つけるサポートが可能です。やりがい・環境・成長のバランスを考慮した提案で、納得のいく選択を後押しします。
まずは無料相談から。一緒に「納得のいく転職」を目指そう
「転職するかどうか決めきれない」「まずは話を聞いてみたい」そんな段階からでも、Cocottoの無料キャリア相談をご利用いただけます。相談はオンラインOK、もちろん無理な転職のすすめは一切ありません。あなたの今の状況や悩みを整理し、選択肢を広げるお手伝いをします。仕事も人生も“納得感”が大切。ひとりで抱え込まず、キャリアのプロと一緒に、次の一歩を考えてみませんか?まずは気軽にご相談ください。
「経験が浅いから不安…」「こんな理由で転職していいのかな?」そんな悩みもCocottoなら大丈夫。
あなたのペースに寄り添いながら、理想の働き方や職場を一緒に見つけていきます。
無理なく納得のいくキャリアを歩むために、まずは無料でプロに相談してみませんか?
▶️ [Cocottoに無料相談する]
share on



 転職相談はこちら
転職相談はこちら お問い合わせ
お問い合わせ
