新卒で退職を考えたら?失敗しない退職の仕方と退職代行の活用法・注意点を徹底解説
企業名が入ります
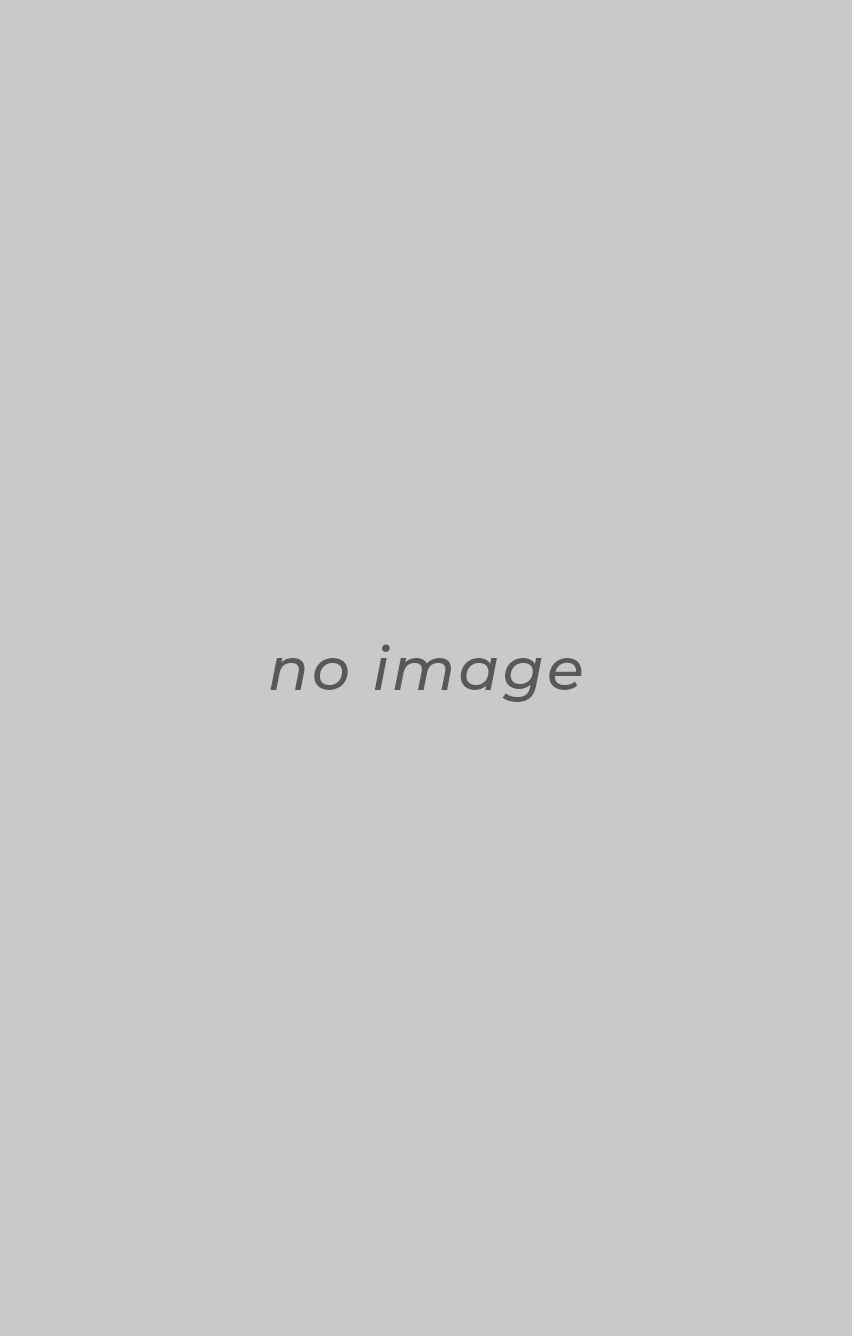
新卒が退職を考えるのは「甘え」じゃない
退職を考える新卒は実は少なくない
新卒で入社したものの「このままでいいのかな」と感じている人は、決して少数派ではありません。社会に出て初めての職場で理想と現実のギャップに戸惑うのは、ごく自然なこと。厚生労働省の調査でも、新卒の3人に1人が3年以内に離職しているというデータがあります。「こんなことで辞めたら甘い」と自分を責める必要はありません。大切なのは、自分の気持ちを無視せず、今の環境が本当に自分や目指すキャリアに合っているのかを冷静に見極めることです。悩んでいるのはあなただけではないという事実を、まずは知っておきましょう。
離職の理由は「人間関係」や「理想とのギャップ」が多数
新卒の離職理由としてよく挙げられるのが、「職場の人間関係が合わない」「思っていた仕事と違う」といった理想と現実のギャップです。特に社会経験が少ない新卒にとっては、価値観の異なる上司や同僚との関係構築は大きなハードルになります。また、就活時にイメージしていた仕事内容との乖離があると、「この先も続けて大丈夫なのだろうか」と不信感や不安を抱えることも。こうした悩みは誰にでも起こりうるもの。だからこそ、「自分に問題がある」と思い込みすぎず、今の状況にどう対応すべきかを客観的に考えることが大切です。
まずは「辞めたい理由」を整理してみよう
退職を考えたときに最初にすべきことは、「なぜ辞めたいのか」を言語化することです。上司との関係に悩んでいるのか、仕事そのものに不満があるのか、漠然とした不安なのか―原因が明確になることで、自分に必要な行動が見えてきます。ノートやスマホのメモに思いつくままに気持ちを書き出してみましょう。人に話すことで整理できる場合もあります。自分の心の声に耳を傾けることは、今後のキャリアを見つめ直す大切な一歩。衝動的な判断を避けるためにも、まずは「理由の棚卸し」をしてみることをおすすめします。
仕事を辞めたいと思ったときにまず確認すべきこと
辞める前に知っておきたい手続き・ルール
退職を決めたら、まずは基本的なルールや手続きを理解しておくことが重要です。民法上では「2週間前の申告」で退職は可能ですが、就業規則で「1カ月前に申し出ること」と定められている企業も少なくありません。退職届の提出タイミングや引き継ぎの流れ、有給休暇の消化、保険や税金の手続きなど、やるべきことは意外と多いもの。感情的に辞めるのではなく、円満退職を目指すためにも、事前に制度や流れを確認しておきましょう。職場に迷惑をかけずに退職する姿勢は、次のキャリアにも好影響を与えます。
退職が確定するまでのスケジュール感
退職の意志を伝えてから実際に辞めるまでには、ある程度の時間がかかります。一般的には、退職希望日の1カ月前に上司へ申し出を行い、社内での承認を経て退職届を提出。その後は業務の引き継ぎや書類の準備、最終出勤日の調整などが進められます。有給休暇を活用する場合は、日数によって実働期間が短くなることも。退職代行を利用する場合でも、書類のやりとりや会社側の手続きには一定の時間が必要です。焦って動くのではなく、スケジュールに余裕を持って計画を立てることで、心にもゆとりが生まれます。
信頼できる人への相談・報告も忘れずに
退職は個人的な決断とはいえ、家族や身近な人への相談や報告も欠かせません。特に新卒や若手の場合、初めての退職に不安を感じるのは当然のこと。自分だけで抱え込まず、信頼できる人に気持ちを打ち明けることで、冷静に状況を整理できることもあります。家族からのアドバイスが心の支えになることもあるでしょう。また、事後報告ではなく、早めに話すことで周囲の理解や協力も得やすくなります。退職を「一人で乗り越えるもの」と思い込まず、頼れる相手には素直に気持ちを伝えることが大切です。
退職の基本知識と新卒が知っておきたい注意点
新卒の早期退職でキャリアに影響はある?
新卒で早期退職を検討する際、多くの人が「経歴に傷がつくのでは?」と不安になります。しかし、現代では「自分に合わない職場に固執しない判断力」として評価されるケースも増えてきています。もちろん、退職理由やその後の行動によって印象は変わるため、退職を選ぶことで次のキャリアはどのように築き直すかを考えてるかが大切になってきます。ただ早期退職=マイナスと捉えるのではなく、自分自身の成長や適職・今後のビジョンを見極める機会と捉えましょう。大切なのは、辞めたことよりも「辞めたあとにどう動くか」です。早期退職を繰り返すことのないように、しっかりここのフェーズで自分と向き合いましょう。
退職理由はどう伝えるべきか
退職を決意したら、上司にどのように理由を伝えるか悩む人も多いでしょう。感情的になったり、ネガティブな内容をそのまま伝えたりすると、円満退職が難しくなることも。基本は「個人的なキャリアの方向性」や「価値観の違い」など、前向きな表現に言い換えることがポイントです。たとえば「新たな環境でスキルを伸ばしたい」「自分の適性を見直したい」といった形で伝えることで、相手の受け取り方もやわらかくなります。退職は今後のキャリアにも影響するため、感傷的・感情的にならず最後まで丁寧な対応を心がけましょう。これも今後の自分に繋がっていきます。
今後の転職活動に向けてしておくべき準備
退職後スムーズに次のステップへ進むためには、事前の準備がカギです。まずは自己分析を行い、「自分はどんな仕事・職場が合うのか」やビジョンを明確にしましょう。また、履歴書・職務経歴書の作成や、面接での退職理由の答え方も早めに準備しておくと安心です。新卒での早期退職者を歓迎する企業もあるため、第二新卒向けの求人を多く扱う転職エージェントに相談するのもおすすめです。ポイントは「焦らず、じっくり」と。自分に合ったキャリアを描いていきましょう。
退職代行サービスの活用法と注意点
退職代行を使うメリット:即日退職・直接報告不要
退職代行を利用する最大のメリットは、「自分で退職の意思を伝えなくていい」点にあります。上司への報告や引き止めをストレスに感じる人にとっては、大きな負担軽減になります。また、サービスによっては即日で退職の意思を会社へ伝えてくれるため、精神的に限界を迎えている人にとって非常に心強い存在です。新卒の早期退職も対応している業者が多く、労働問題に詳しい弁護士や労働組合が運営するサービスもあるため、安心して利用できる体制が整ってきています。
デメリットとリスク:費用、信頼性、職場への印象
退職代行は便利な反面、デメリットも理解しておく必要があります。まず費用面では、一般的に2〜5万円程度かかり、経済的に余裕のない新卒には負担になることも。また、業者の中には実績が不透明でトラブルの報告があるところもあるため、信頼性の高いサービスを見極める力が必要です。さらに、代行を使うことで職場に「逃げた」という印象を与える可能性もゼロではありません。今後のキャリアや人間関係への影響を踏まえたうえで、代行サービスを使うかどうか慎重に判断することが大切です。
「使うべきケース」と「使うとリスクのあるケース」
退職代行は、精神的に追い詰められていて職場と一切やりとりしたくないときや、ハラスメントがある場合に有効な手段です。誰にも相談できず、限界を感じているなら、退職代行を通じて安全に離職する選択は決して間違いではありません。一方で、引き継ぎや社会保険の手続きが未完了のまま利用すると、後々トラブルになる可能性も。職場との関係が極端に悪化していない場合や、自分で冷静に話せる余地があるなら、まずは自力での退職交渉を検討してみるのも一つの手です。
自分で退職手続きをする場合と退職代行を使う場合の流れ
自分で退職する場合:上司への報告から退職確定まで
自分で退職の手続きをする場合、まずは直属の上司へ退職の意思を伝えることがスタートです。口頭または書面で申し出た後、人事部門との面談や退職日の調整、業務の引き継ぎなどを経て、正式に退職が確定します。退職願は少なくとも1か月前には提出するのが一般的で、社会保険や源泉徴収票などの手続きにも注意が必要です。円満退職を目指すなら、誠実なコミュニケーションと、最後まで責任ある行動を意識しましょう。スムーズな退職は、次のキャリアに確実に好影響をもたらします。
退職代行に依頼する場合:依頼から対応、確定までの流れ
退職代行を利用する場合は、まず退職希望日や相談内容を業者に伝え、正式に契約を結びます。依頼が完了すると、業者が会社側に退職の意思を伝達し、以降の連絡もすべて代行されます。本人は出社や連絡対応をする必要がなく、スムーズに退職手続きが進むのが特長です。弁護士や労働組合が運営するサービスなら、法的トラブルにも対応可能です。ただし、会社によっては書類のやりとりや私物の整理など、一定の対応が必要なケースもあるため、代行サービスがどこまで対応してくれるのか事前確認をしっかり行いましょう。
失敗しないための注意点とチェックリスト
退職を円滑に進めるためには、事前準備と確認が欠かせません。まず「退職理由」を明確にし、退職希望日や有給の扱い、社会保険・税金関連の流れをチェックしましょう。退職代行を使う場合も、信頼できる業者を選び、契約内容や対応範囲を理解することが重要です。必要に応じて、家族や第三者への相談もしておくと安心です。また、転職活動とのタイミング調整も忘れずに。慌てて辞めて後悔しないためにも、「辞めた後」のことまで視野に入れて行動しましょう。
ハラスメントに悩んでいる人へ|一人で抱え込まないために
「今日もう辞めたい」と感じるほどのストレスを感じたら
新卒で社会人生活を始めたばかりの頃、「今日もう辞めたい」と強く感じるほどのストレスを抱えることは珍しくありません。仕事のプレッシャーや人間関係の悩み、慣れない環境による疲労が重なり、心身ともに追い詰められてしまうこともあります。そんな時は、一人で抱え込まず、まずは信頼できる人や専門機関に相談することが大切です。無理を続けると、精神的な健康を大きく損なう恐れがあるため、適切な対処を早めに取ることが重要です。また、退職を考える場合でも、冷静に計画を立てて行動することが、後悔しない選択につながります。
新卒が声を上げづらい職場環境の実態
新卒社員は職場での立場が弱いため、問題や不満を声に出しづらいのが現実です。上司や先輩に逆らいにくい雰囲気や、まだ仕事に慣れていないことから、「我慢するしかない」と感じてしまいがちです。また、社内のハラスメントや理不尽な業務の強要に対しても、訴える場所や方法がわからないことも少なくありません。このような環境が続くと、精神的に追い詰められ、離職に繋がるケースも多いです。だからこそ、社外の相談窓口を活用したり、信頼できる第三者に相談することが大切です。自分の声を無理に抑え込まず、適切なサポートを求めましょう。
⇒厚生労働省【総合労働相談コーナー】
パワハラ・モラハラなど、退職代行の使用が有効な場面
パワハラやモラハラなど、職場での深刻な人間関係トラブルがある場合、退職代行サービスの利用は有効な手段の一つです。特に、新卒であっても直接上司や人事に退職の意思を伝えることが困難な状況では、専門の退職代行業者に相談することで、精神的な負担を軽減できます。ただし、退職代行には利用時の注意点もあり、会社とのトラブルを避けるために事前に契約内容やサービス範囲をよく確認することが重要です。法的トラブルを防ぎ、スムーズに退職するために、信頼できる業者を選ぶことがポイントとなります。
まとめ|退職を考えたら、まずは転職エージェントを頼ってみよう
キャリアの棚卸しと今後の方向性を一緒に考えられる
退職を考え始めたときこそ、自分のキャリアと向き合う絶好のタイミングです。ただ、何をどう考えたらいいか分からないという方も多いでしょう。そんなときに頼れるのが、転職エージェントの存在です。これまでの経験やスキル、適性を一緒に整理しながら、将来に向けた方向性を一緒に考えてくれます。新卒や社会人経験が浅い方でも、面談を通じて自分では気づかなかった強みや可能性が見つかることも。今の職場にとどまるべきかなどの直近の判断から将来的な範囲まで納得のいくキャリアを描く第一歩として、まずは気軽に相談してみましょう。
新卒・第2新卒向けの非公開求人も豊富
転職エージェントを利用するメリットの一つは、一般には出回っていない「非公開求人」を紹介してもらえる点です。特に新卒・第2新卒向けの求人は、企業側も若手を育てたいというニーズがあるため、近年ポテンシャル重視の採用枠が多く設けられています。こうした求人は、エージェントを通じて初めて知ることができるものが多く、応募者一人ひとりの希望や適性に合った職場と出会いやすくなります。今の環境が合わないと感じているなら、「自分に合った会社は他にもある」と知ることで、次の一歩を踏み出す大きな勇気になります。
退職・離職からの再スタートをサポート
退職や離職を経験すると、「この先どうすればいいんだろう」と不安になるものです。特に新卒での早期退職は、後ろめたさや自信の喪失につながりやすいですが、そんな時こそプロのサポートが力になります。転職エージェントは、履歴書や職務経歴書の書き方、面接対策、企業とのやりとりまで丁寧にフォローしてくれます。離職中の期間があっても、それをどう前向きに伝えるかなど、状況に応じたアドバイスも受けられます。退職はゴールではなく、新しいスタート。焦らず、着実に次のステップを踏み出していきましょう。
\ あなたのキャリア構築をプロが伝授! /
👉 自分に合った仕事・職場で働く|Cocotto無料転職相談はこちら
share on



 転職相談はこちら
転職相談はこちら お問い合わせ
お問い合わせ
